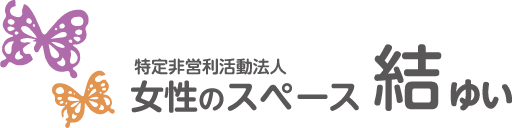~世界における日本のジェンダーの状況について~
講師:神奈川大学 法学部教授 井上 匡子氏
講座開始の冒頭に、井上氏の好きな言葉は“痛みを力に”というお話があり、井上氏の優しさや温かさを感じる講座でした。

●ジェンダーギャップ指数
世界経済フォーラム「ジェンダー・ギャップ指数2023」は経済、政治、教育、健康の4つの分野のデータから作成された。日本は146か国中125位。過去最低であり、主要先進国(G7)のなかで最下位である。教育・健康は世界トップクラスだが 政治・経済の参画の値が低い。
●DVに対して、世界の中の日本
今回5回目の法改正が行われ、保護命令に精神的暴力が入ったことは少し前進。加害者プログラムの義務付け(シンガポール)や、警察や家庭裁判所を中心としたシステム(韓国)民間の若いスタッフと公的機関とのバランス(台湾)など、諸外国も最初は小さくスタートして、その後、制度を育ててきた。知らない人同士の暴力(街頭暴力)と、親密な関係のDVでは対応が異なる。DVケースの離婚はきちんとした形で手続きしていく必要があるが、困難なケースほど民間に回って来ざるを得ない状況。しかし、法的位置づけがまだ無い。その背後にあるジェンダー構造への理解が必要。妻にも問題があるんじゃないの?という考え方こそがジェンダーの根っこである。
●GBV(gender based violence ジェンダーに基づく暴力)としてのDV
性の2元的構成(第2波フェミニズム)は、セックスvsジェンダーとなり、性の四要素へつながる。生物学的(戸籍・外見はどこの国でも同じ認識での性)な面だけでなく、社会的・文化的(産業構造からうまれる性で①多様性②家父長制・権力性)な面がある。
●性の四相
1,生物学的性(Sex)身体の性、戸籍の性
2,性自認(Gendar Identity)自分が思う性
3,性的指向(Sexual Orientation)対象の性、恋愛感情や性的関心が向く方向
4,性表現(Gendar Expression)社会的な性、性役割
性の四相とそれぞれの多様性は、境界はグラデーション(連続性)であり、レインボーである。
●権力としてのジェンダーと序列化
構造化したジェンダー(ジェンダー構造)は見えにくい。(むしろ見えない)
マジョリティは見えない。→無意識のうちに、権力や構造の再生産に加担している。
マイノリティは見える、感じる。→常に構造に傷つけられている。
マジョリティでもアンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)を抱えていることをその人自身が理解する必要がある。
ぴったりとサイズの合う靴がある人にはわからないが、合わない靴を履かざるを得ない人は、靴を脱いでは外を歩けないつらさを持っている。
<アンケート結果>
・暴力はどの立場もやってはいけないが、育った環境、境遇により、意識の中に根付く感覚
は人それぞれ違うだろう。夫婦など、パートナーとの関係において、それぞれの思いや、
価値観が異なるという「教育(性教育含め)」が必要だと感じた。その人のジェンダー
(性、構造)を認め合って理解し合える関係が、夫婦、職場、学校などあらゆる場面で築
けるとSDGsの5が達成できていくのかなと思った。
・ジェンダーについて 今までと違う角度から知ることが出来た。
・すごろくを通して、自分に向き合って考えることが出来た。 参加するごとに、自分の今までの考えに向き合い、差異を考えるきっかけになっている。平和学に興味を持った。
◆明日からでもできるサポートとは?
・暴力と感じることにまず声をあげること
・他人の話を その人の背景を想いながら聞くこと。
・とりあえず、いま所属する団体の仕事を真面目にする。
日常生活では、誰か他人から、「あなたのご主人は~」と言われたら、
「私の主人は私ですよ。夫の事を言っておられるなら、『夫』は『主人』ではないです」とやんわり返す。
それから、これから結婚しようというカップルがいたら、「どっちの名前にするの?」と聞いて、
女性が名前を変えるのが当たり前という意識を揺さぶってみる。